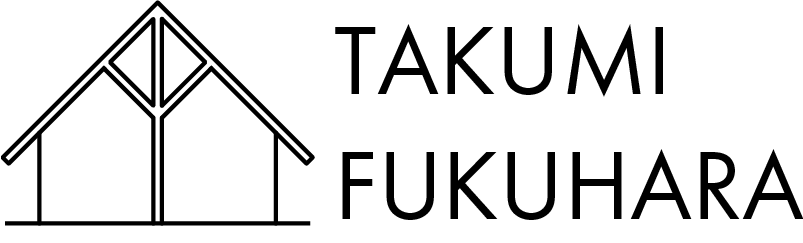2019.08.B3
設計製図第四 意匠スタジオ
出題者:増田信吾(増田信吾+大坪克亘)
「Diagnostic Designing -Anti-vision-」
Site Problem
藤沢駅南口駅前広場に面する通称「391街区」と呼ばれる街区であり、内部で連結された3棟の再開発ビルと、それに囲まれた方形の中庭(ハゼの木広場)から構成される中庭型街区という特徴的な携帯を有している。地下1階、地上6〜7階の3棟のビルには、現在もスーパー、大型書店、雑貨屋、飲食店などの店舗が入居している。しかし、近年では商業的競争力の低下などの問題も抱えている。
この街区は1975年には買周り性向上の為に3棟のビルがエキスパンションジョイントで連結された。空地は採光のためだけではなく、設計者の石川允と菅原文哉の「ビルの真ん中に広場をとって、ファザードは広場に向けようや」というヴィジョンを実現する為の措置であったとされている。
また、このビルの設計手法は石川栄耀が提唱とした「Terminal Vista」の考えを踏襲している。これは各アプローチ街路からの視線は広場を通過しないというもので、包まれた感じが正直人を集めるための広場の要諦であるとされた。
Diagnosis
この街区には、石川栄耀の提唱するTerminal Vistaに基づく広場を中心としたヴィジョンが存在していた。それが以下の要因によって、齟齬が生じていると捉えた。
1.建物の高さに比して、広場の広さが十分で薄暗い。
2.3棟が繋げられることに、ビルの裏導線と面導線が交錯してしまっている。
3.Terminal Vistaの性質上、人目の不届きな空間が生じ、藤沢駅周辺での負のモノを吸収している。
以上から、主に中庭周辺に操作を加えることにとって中庭、そして建物全体までもの価値を向上されることに尽力を注ぎたい。また、操作においてはこの建築の1番の魅力である、秩序のある溢れ出しを生かす計画とする。
Treatment
施術の流れは以下の通り
1.圧迫感や暗さなどの不快感の原因でもある壁を取り払う。
2.壁が裏導線を生んでいることから、裏導線を移転し、回遊性を持たせる。
3.中庭に人が集まれるような仕組みを作る。
4.各階のスラブはその溢れ出しを包括するように形状を変化させ。
5.次元から3次元化したファザードは、この建物がもつ圧迫感を制限し、さらに、新たに中庭側にファザードが向けられるようになっている。
6.中庭にとっては各階のスラブもファザードとなる。ステンレス製のスラブは光を中庭に集めるとともに、溢れ出した様子をも中庭へと集められる。